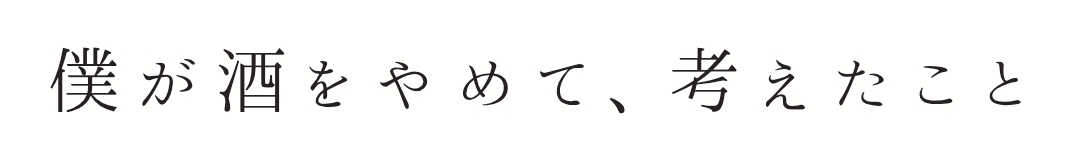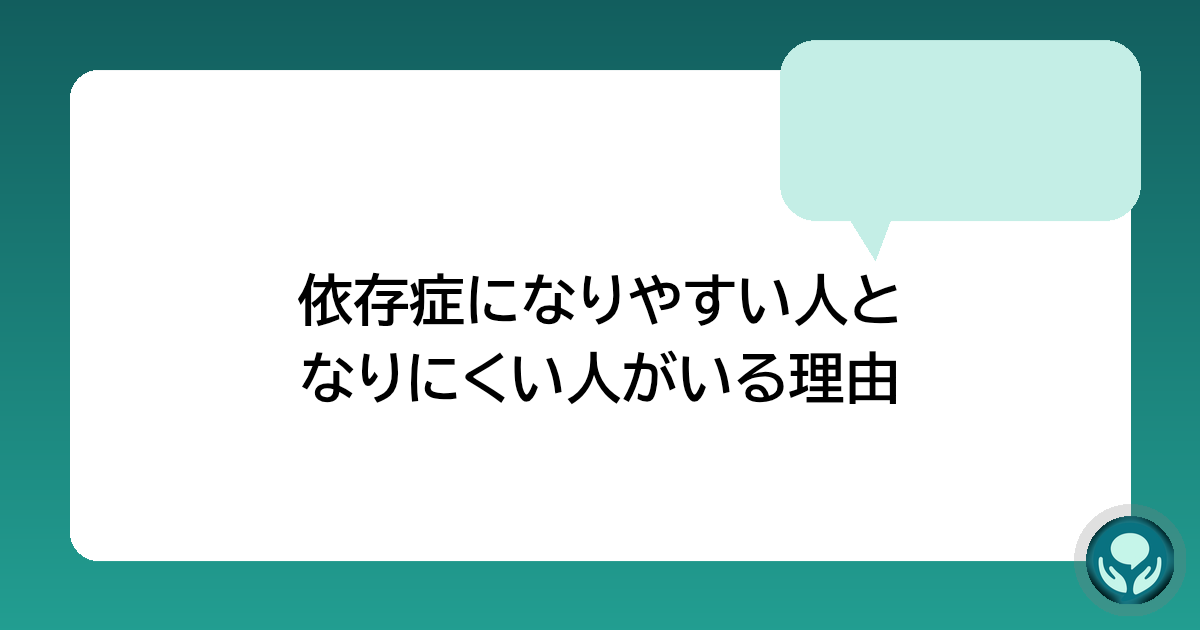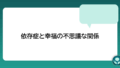私たちの周りには、お酒やギャンブル、買い物など、心を惹きつけるものがたくさんあります。
多くの人がそれらを楽しみ、日常の彩りとして上手に付き合っています。
しかし、その一方で、気づけば「それなしではいられなくなり」、心と体を蝕まれてしまう人々がいます。
それが「依存症」です。
「だらしないから」「意志が弱いからだ」——。
かつて、依存症は個人の性格や道徳の問題として片付けられがちでした。
しかし、多くの研究や当事者の声から、それは単純な「本人のせい」では片付けられない、もっと根深く複雑な問題であることがわかってきました。
では、同じようにお酒を飲んでいても、依存症になる人とならない人がいるのはなぜなのでしょうか。
その境界線は、どこにあるのでしょうか。
心の「痛み」を和らげる鎮痛剤
まず、依存症のメカニズムについて、少し視点を変えてみましょう。
一般的に、依存は「快楽を追い求めた結果」だと思われがちです。
しかし、多くのケースでは、「耐え難い苦痛から逃れるため」に始まります。
誰にも言えない孤独感、過去の辛い記憶、自分を責め続ける自己否定感…。
こうした心の痛みを、アルコールや特定の行為は一時的に麻痺させてくれます。
まるで、強力な「鎮痛剤」のように。
つまり、依存症の入り口は「快楽」ではなく「救済」なのです。
問題は、その鎮痛剤が、長期的には心と体をさらに深く傷つける「猛毒」に変わってしまうこと。
そして、その鎮痛剤を特に必要としてしまう心の状態がある、ということです。
違いはどこから?「内的環境」という心の土壌
では、その「鎮痛剤」を強く求めてしまう人と、そうでない人の違いは何なのでしょうか。
その一つが、その人の「内的環境」、つまり心の土壌にあります。
私たちの物事の捉え方や感じ方の土台は、多くが幼少期に形作られます。
例えば、いつも安心できる環境で育った子どもは、世界を「安全な場所」だと感じ、困難があっても「なんとかなる」と思える自己肯定感を育みやすいでしょう。
しかし、もし家庭が常に緊張感に満ちていたり、ありのままの自分を受け入れてもらえなかったりする「サバイバル体験」をしながら育ったとしたらどうでしょうか。
その場合、世界は「危険な場所」としてインプットされ、常に不安や恐怖に備える心の癖がついてしまうことがあります。
こうした「生きづらさ」を抱えた心の土壌では、ささいな出来事も深刻な「問題」として捉えられがちです。
そして、その過大なストレスに対処するための健全な方法(誰かに相談する、趣味で発散するなど)を学ぶ機会がなかった場合、最も手軽で強力な鎮痛剤であるアルコールなどに頼らざるを得なくなってしまうのです。
つまり、依存症になりやすいかどうかは、その人がもともとどんな心の土壌を持っているか、そしてストレスに対処するための健全な道具(コーピングスキル)をどれだけ持っているかに大きく左右されるのです。
社会という「外的環境」が背中を押すとき
個人の「内的環境」に加えて、私たちが生きる社会、つまり「外的環境」も大きな影響を与えます。
特に日本は、アルコールに対して非常に寛容な社会です。
仕事の付き合いで「飲みニケーション」が推奨されたり、メディアがお酒の楽しい側面ばかりを映し出したり…。
まるで、飲酒がストレスを解消するための「公認スキル」であるかのような雰囲気があります。
このような社会では、心の痛みを抱えた人がアルコールに救いを求めることへのハードルは非常に低くなります。
脆弱な心の土壌(内的環境)を持つ人が、強いストレス(職場や家庭の問題)にさらされ、なおかつアルコールに寛容な社会(外的環境)にいる——。
これら三つの要素が重なったとき、依存症という名の嵐が発生するリスクが、極めて高くなるのです。
「意志の弱さ」ではなく「理解と支援」を
ここまで見てきたように、依存症は決して特別な誰かの問題ではありません。
心の土壌、ストレス、そして社会的・文化的な背景が複雑に絡み合って生まれるものです。
もしあなたの周りに苦しんでいる人がいたら、「意志が弱い」と責めるのではなく、その人がどんな「痛み」を抱え、どんな土壌の上を歩いてきたのか、少しだけ想像してみてください。
依存症は、その人が必死に生き延びようとした結果、たどり着いてしまった「孤立の病」でもあります。
その孤立から抜け出す第一歩は、私たちの社会がこの問題を正しく理解し、責めるのではなく、回復への道をそっと照らす温かい支援の輪を広げていくことなのかもしれません。

アルコール依存症当事者です。
2020年7月から断酒しています。
ASK公認依存症予防教育アドバイザー8期生