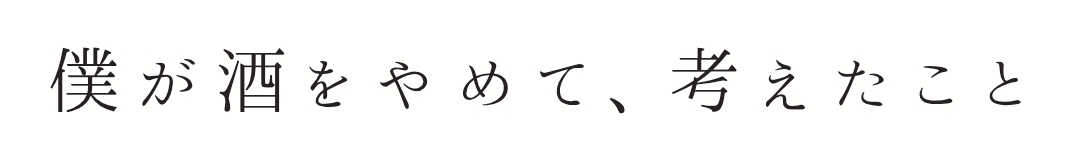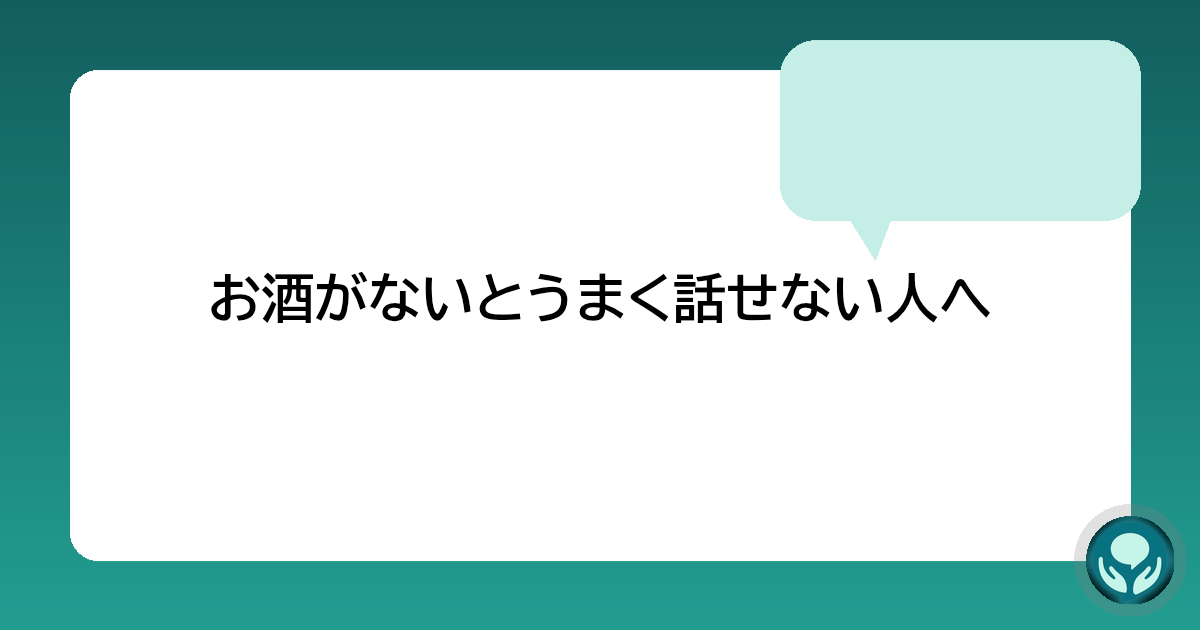「自分は、人と話すのがあまり得意ではない」
そう感じている方は、決して少なくないのではないでしょうか。
雑談の輪にうまく入れなかったり、初対面の人との会話に緊張してしまったり。
コミュニケーションにおける、そうした一つ一つの小さなつまずきが、日々の「生きづらさ」に繋がることがあります。
そして、この困難をいとも簡単に解決してくれるように見える、魔法のような存在があります。
それがアルコールです。
今回は、多くの人が経験する「お酒の力を借りたコミュニケーション」の裏側で、一体何が起きているのかを、丁寧に見つめていきたいと思います。
「道具」としてのアルコール、その魅力
コミュニケーションは、人間が社会で生きていく上で、極めて重要な能力です。
それがうまくできないことから生じる様々な不具合を、多くの人は、アルコールという物質の力によって補おうとします。
アルコールには、脳の働きを抑制し、理性の働きを一時的に緩和させる作用があると言われています。
普段は「こんなことを言ったらどう思われるだろう」「うまく話さなければ」といった、過剰な自意識や緊張が、アルコールの摂取によって和らぎます。
その結果、いつもより饒舌になったり、陽気になったり、普段は言えないような本音を話せたりすることがあります。
この体験は、非常に強い成功体験として心に刻まれます。
コミュニケーションが苦手だ → お酒を飲むと楽になる → やはり、自分にはお酒が必要なんだ。
この一連の流れは、アルコールを「コミュニケーションを円滑にするための、必要不可欠な道具」だと脳に強く刷り込んでいきます。
この「認知の強化」こそが、アルコールへの依存を形成していく上での、最初の、そして最も重要な一歩となることがあるのです。
人間的な対話 vs 本能的な反応
では、その強力な「道具」を使い続けると、長期的には何が起こるのでしょうか。
ここで重要になるのが、「人間的なコミュニケーション」と「本能的なコミュニケーション」という視点です。
本来、人間的なコミュニケーションとは、相手の話に耳を傾け、その意図を汲み取り、自分の考えを理性的に整理して言葉にする、という複雑なプロセスを伴います。
そこには、相手への配慮や共感、そして自己コントロールが不可欠です。
しかし、アルコールによって理性が緩和された状態では、こうした高度な働きが少しずつ鈍くなっていきます。
代わりに優位になるのが、より衝動的で、自己中心的な、本能に近い反応です。
相手の話を遮って自分の話をし始めたり、感情的な言葉をぶつけてしまったり。
それは一見、活発なコミュニケーションに見えるかもしれませんが、その実態は、丁寧な対話とはほど遠いものです。
皮肉なことに、コミュニケーションのために使い始めたはずの道具が、長期的には、相手を深く理解し、自分を正しく伝えるという、最も人間的なコミュニケーションの能力を少しずつ蝕んでいくのです。
「お酒がないと話せない」という認知は、ますますアルコールへの依存を深めます。
しかし、頼れば頼るほど、人間的な対話は失われ、結果として深い誤解や孤独感に苛まれていく。
これが、この問題の持つ深刻な悪循環です。
道具を手放し、自分の声を取り戻す
依存症からの回復とは、この便利で、しかし危険な「道具」を手放し、コミュニケーション能力をゼロから作り上げていくプロセスとも言えます。
自助グループなどで、多くの回復者が「言いっぱなし・聞きっぱなし」といった、安全性を最大限に重視したルールの中で対話を学ぶのは、まさにこのためです。
そこでは、上手な話をする必要はありません。
ただ、不器用でも、正直に、自分の言葉で内面を語ることが奨励されます。
「お酒がないと話せない」のではありません。
「お酒の力を借りないと、上手なコミュニケーションができない」と感じていただけなのかもしれません。
回復とは、その「上手であること」へのこだわりを手放し、たとえ拙くとも、ありのままの自分の声で人と繋がる喜びを、もう一度学び直していく、長く、しかし希望に満ちた旅路なのです。

アルコール依存症当事者です。
2020年7月から断酒しています。
ASK公認依存症予防教育アドバイザー8期生