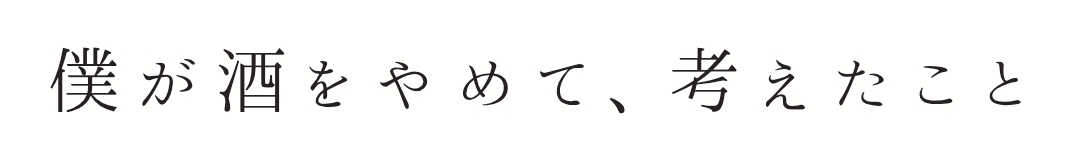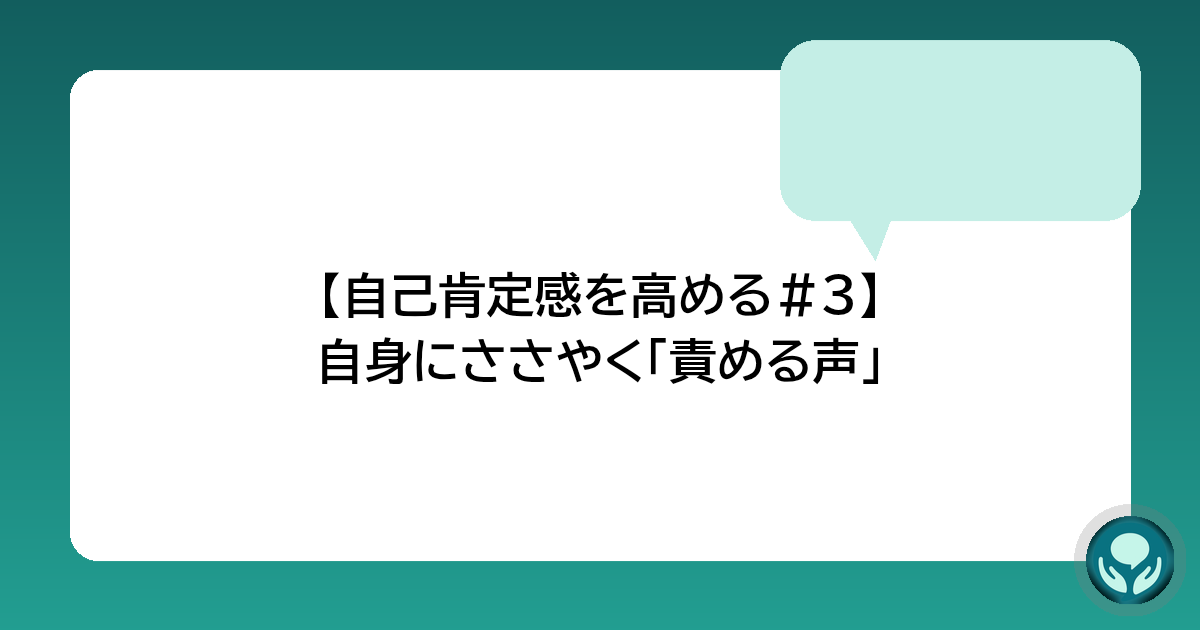(第2回より)
「また失敗した」「自分は弱い」――気がつくと、頭の中で自分を裁く声が鳴っています。
私がアルコールに頼っていた頃、この声は常に大きく、黙らせる手段がお酒しかないと信じ込んでいました。今振り返ると、その声の正体は他人のまなざしを自分の内側に取り込んだものでした。
周りの期待に応えるために“理想像”を演じ、本当の気持ちを抑え込む。やがて「ありのままの自分」を認められなくなり、息苦しさが日常になっていきます。
自己肯定感は「理由がなくても自分にOKを出せる力」です。根拠はいりません。
ところが、幼い頃から「できたら褒められる」「役に立てば価値がある」といった条件付きの価値観にさらされると、私たちは無意識に「条件を満たさねばならない」という回路を作ります。
この回路が動くと、“責める声”は簡単に起動します。
出来事と解釈を分けてみる
自分を責めるとき、実は私たちは出来事そのものではなく、それに付けた解釈に反応しています。
例を挙げます。上司に指摘された(出来事)。そこで「私は期待に応えられない人だ」解釈と受け取ると、恥や不安が生まれ、過剰な残業や回避に走る(行動)。結果、消耗と自己嫌悪が残る。
この流れはとても素早く、ほとんど反射のように起こります。だからこそ、出来事と解釈を切り分けるだけで、責める声に小さな隙間が生まれます。
私が実感したのは、自己肯定感の“回復”とは、大それた改革ではなく、この小さな隙間を作る技術だということです。隙間ができれば、呼吸が戻り、選択が戻る。お酒ではなく言葉で自分を解放できるようになりました。
偽りの自分が生む息苦しさ
「完璧でない自分は許せない」という感覚は、自己肯定感の低さをもっとも手早く悪化させます。
理想像に自分を合わせようとするほど、本来の感情は“騒音”として扱われ、さらに抑え込まれる。
私は長い間、恥ずかしさや弱さを見せないことで身を守っているつもりでしたが、実際は自分を否定し続けていただけでした。
転機は、自助会で「認めたくなかった自分」を人前で言葉にしたときです。恥ずかしさは消えませんでしたが、「それでも私はここにいていい」という感覚が、胸の奥に初めて芽生えました。
この体験は、自己肯定感が「成果の総和」ではなく、「無条件の肯定」でしか回復しないことを、身体レベルで教えてくれました。
「外側」では埋まらない
依存症の根っこには、心の欠損を外側で埋めようとする動きがあります。お酒でも、仕事でも、承認でも、一瞬は満たされる。しかし外側のものは、私たちの心の所有者ではありません。外側が去れば、また空洞が戻る。
自己肯定はその逆です。自分の心は自分にしか扱えないという事実を受け入れ、内側から「OK」を出す。これができるほど、外側への過剰な依存は弱まります。
ふと気づいたときだけ使う、軽い確認
ここでは「軽い確認」が役立つ場合があります。
これは事実? それとも私の解釈?
例:「メールの返信が遅い」までは事実。「嫌われた」は解釈。事実に立ち戻るだけで、責める声は音量が下がります。
私は今、何を感じている?
言葉が出ないときは、肩・胃・喉などの違和感を手がかりにする。感情は情報であって、善悪の判定ではありません。
どれも数秒で終わり、メモも不要です。思考=事実ではないと気づけた瞬間、その回路は弱まります。
まとめ―責める声に、居場所を与えない
- 自己肯定感は「根拠のないOK」。条件付きの価値観がそれを覆い隠す。
- 責める声は、出来事ではなく解釈から生まれる。切り分ければ隙間ができる。
- 偽りの自分を続けるほど、感情は騒音になり、息苦しさが増す。
- 心の欠損は外側では埋まらない。自分が自分に出すOKだけが持続する。
“責める声”は、あなたの本質ではありません。
その声が立ち上がったら、ただ、短く確かめる。思考は事実ではない。――この小さな確認が、自己肯定感という土台を、静かに、しかし確実に支えていきます。
(第4回へ続く)

アルコール依存症当事者です。
2020年7月から断酒しています。
ASK公認依存症予防教育アドバイザー8期生