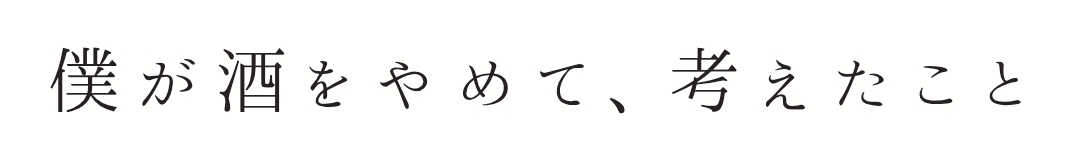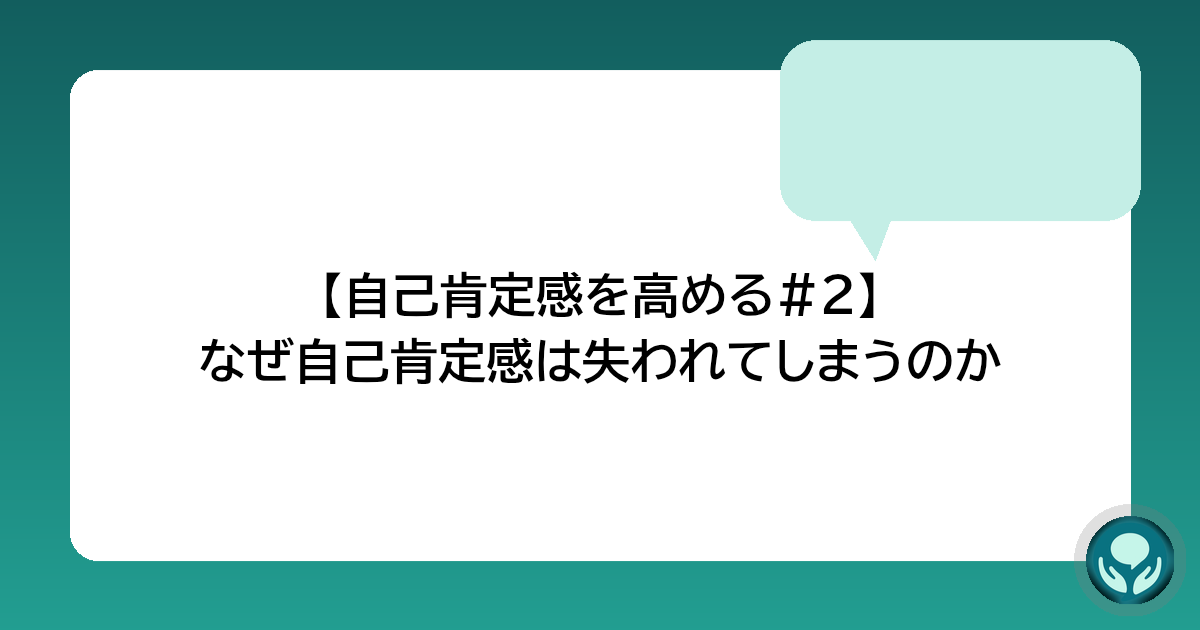(前回の続き)
自己肯定感は、もともと誰もが持って生まれた心の土台です。
赤ちゃんは何もできなくても愛され、泣けば抱っこされ、笑えば笑顔を返してもらえる。そこには「条件付きの価値」なんてありません。
しかし、大人になるにつれて、私たちはいつの間にか「できる自分」「役に立つ自分」でなければ価値がないと思い込むようになります。気づけば、ありのままの自分を認められず、心の奥で「このままじゃだめだ」という声が常に鳴り続けるようになるのです。
幼少期に植えつけられる「条件付きの価値」
自己肯定感が低くなる要因のひとつは、幼少期の経験です。
本来、子どもは存在しているだけで価値があると感じながら育ちます。ところが、次のような出来事が繰り返されると、その感覚が揺らぎます。
- 失敗したときに強く叱られる
- 成績や結果を出したときだけ褒められる
- 感情を否定される
- 家族の期待に応えることが愛される条件になる
こうした環境では、「ありのままの自分」ではなく、「条件を満たした自分」だけが価値を持つという誤った思い込みが育ってしまいます。
子どもの頃は、それが当たり前だと信じます。そして成長しても、その条件を満たし続けなければならないという感覚が無意識に残ります。
成長とともに強化される「他人軸」
大人になると、私たちはさらに外側からの評価にさらされます。
学校では成績や順位、会社では成果や売上、SNSでは「いいね」の数…。社会は他者の評価を基準に動いており、それに応じて人の価値が測られる場面も少なくありません。
もちろん評価は成長を促す側面もあります。しかし、そればかりに依存すると、自分の価値判断がすべて他人任せになってしまいます。
私も長くそうでした。
周囲の期待に応えようと「優等生の自分」を演じ、本音や弱さは隠し続けました。誰かの承認が得られないと、自分の存在そのものが揺らぐような不安に襲われる。これこそが、他人軸の生き方の危うさです。
心の欠損と依存の関係
依存症の背景にも、この自己肯定感の低さがあります。
私はお酒でしか自分を解放できないと思い込み、その時間だけが“本当の自分”を許せる瞬間だと感じていました。素の自分を見せるのが怖く、受け入れてもらえないと確信していたからです。
この状態を別の角度から見ると、「自己肯定感の低さ=心の欠損」です。
その欠けた部分を埋めようとして、人は外部の何か(お酒、買い物、恋愛、仕事など)に依存します。しかし、外部のもので埋められる安心感は一時的で、それがなくなると再び空虚さや不安が押し寄せます。
自己肯定感が低い限り、この循環は繰り返されます。
自己否定は「習慣」になる
もうひとつ重要なのは、自己否定は一度身につくと習慣化するということです。
例えば…
- 失敗したとき、条件反射のように「自分はだめだ」と思う
- 他人と比べて劣っている部分にばかり目が行く
- 何かを達成しないと落ち着かない
- 嫌なことを我慢するのが当たり前になっている
こうしたパターンは長年の経験から作られ、無意識で繰り返されます。意識しない限り、自動的に自己否定が積み重なり、自己肯定感はますます削られていきます。
この「無意識のクセ」に気づくことが、回復のスタートラインです。
自分を責める声の正体を知る
心の中に響く「もっと頑張れ」「まだ足りない」という声は、あなたが生まれつき持っていたものではありません。過去の経験や周囲の価値観が積み重なり、いつの間にか自分の内側に入り込んだ“他人の声”です。
それを自分の本当の声だと信じ続けてしまうと、どれだけ努力しても満たされません。なぜなら、そもそもその声は「今の自分を認めない」という前提で成り立っているからです。
この前提を疑い、手放していくことが、自己肯定感を回復させる大きな一歩になります。
今日のまとめ
- 自己肯定感は生まれながらの資質ではなく、経験によって変化する
- 幼少期の“条件付きの価値観”が低下の原因になりやすい
- 他人軸の生き方は自己否定を強化する
- 自己否定は習慣化し、無意識に繰り返される
- 心の中の「責める声」は、自分本来の声ではない
(第3回へ続く)

アルコール依存症当事者です。
2020年7月から断酒しています。
ASK公認依存症予防教育アドバイザー8期生