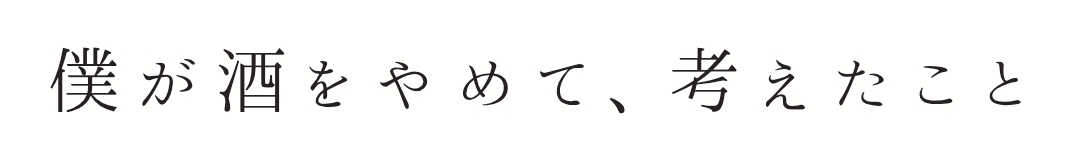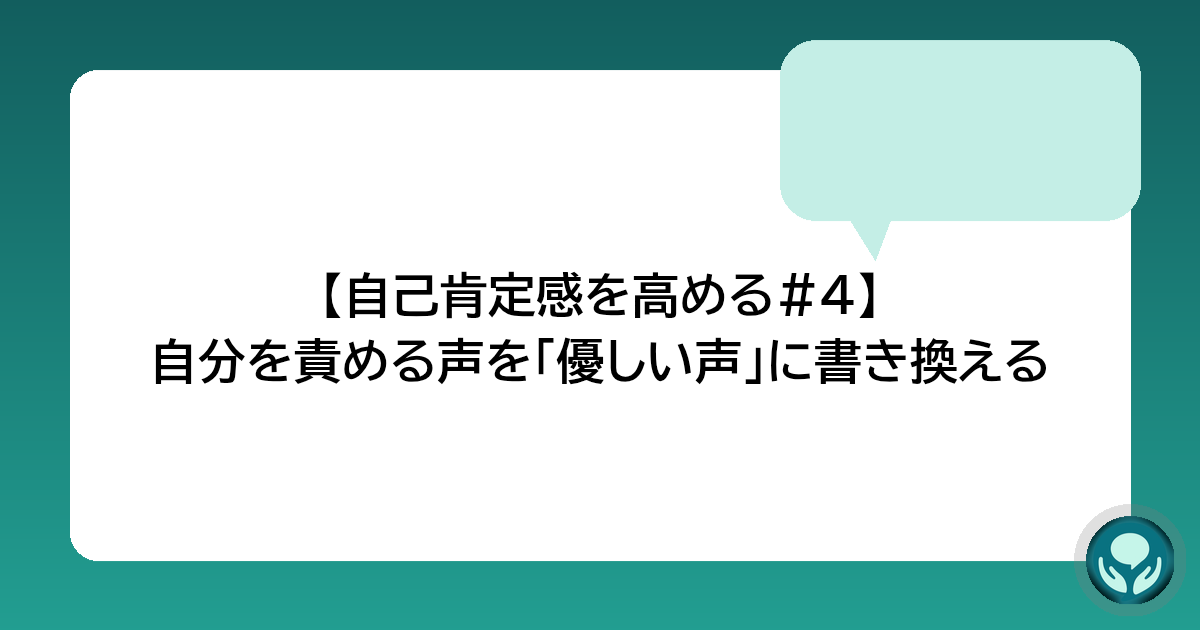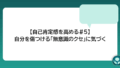(第3回より)
私たちの自己肯定感を蝕む「自分を責める声」。その正体は、出来事そのものではなく、私たちが無意識に付け加えている解釈である、という話をしました。
そして、その声は自分本来のものではなく、過去の経験から内面化された他人の声なのだと。
「思考は事実ではない」――このことに気づき、出来事と解釈の間に「小さな隙間」を作ることが、回復の一助になり得るのです。
今回は、自分を責める声を、自分を育てる「優しい声」に意識的に書き換えていく、より積極的なステップについてお話しします。
なぜ私たちは「自分に優しくする」のが苦手なのか
「自分に優しくしましょう」と言うと、どう感じるでしょうか。
「自分を甘やかすことになる」「成長が止まってしまう」そう考えてはいませんか?
私たちは、特に幼少期の経験から、「自分に厳しくすることが正しい」「完璧でない自分には価値がない」という条件付きの価値観を深く刷り込まれています。
そのため、自分を責めることは「成長に必要なムチ」であり、自分に優しくすることは「怠惰や堕落に繋がるアメ」だと思い込んでしまうのです。
つまり、自分が自分であるために、自分に厳しくするのです。
しかし、これは大きな間違いです。
馬をムチで打ち続けても、走り続けることはできないのと同じです。
馬が走り続けるためには、休息と、栄養と、そして「よくやっている」という労いが必要です。
私たちも馬と同じです。
自分が自分らしくいるためには、自分自身にエネルギーを与えなければならないのです。
心の中の「もう一人の自分」を育てる
では、具体的にどうすれば自分自身にエネルギーを与えられるのでしょうか。
そのコツは、心の中にいる「傷ついた自分」を、自分とは別の、大切な存在として扱ってあげることです。
例えば、あなたの親友が仕事でミスをして、ひどく落ち込んでいたとします。
あなたはその親友に対して、「だからお前はダメなんだ」「もっとちゃんとやれよ」と追い打ちをかけるような言葉をかけるでしょうか?
おそらく、かけないはずです。「大変だったね」「誰にでもあることだよ」「よく頑張ってるじゃないか」と、まずはその苦しみに寄り添い、労いの言葉をかけるのではないでしょうか。
「自分に優しくする」とは、この「親友にかけるであろう言葉」を、自分自身にかけてあげる、ということに他なりません。
自分に優しい言葉をかける習慣
自分を責める声が聞こえることはしょうがないことです。
長年の自己否定の習慣と、知らず知らずのうちに低下した自己肯定感がそうさせているに過ぎないのです。
しかし、それを無条件に受け入れるのは、あまりおすすめしません。
頭の中で自分を責める声が聞こえたら、まずはそこで立ち止まりましょう。自分は今自分自身に対して、酷い言葉をかけていると。
先ほどの親友のたとえを思い出してください。あなたは最も近くにいて、最も大切にすべき親友を傷つけているということです。
「大変だったね」「頑張ってるよ」「よくやってきたね」
そんな言葉を投げかけてみましょう。
意味のないことだと考えるかもしれません。でも、試すのはタダです。少しでもあなたの心がホッとすればそれは価値のあることなのです。
あなたの無意識に、新たな選択肢を与える事ができれば儲けものです。つまり、あなたは今まで自分を責める言葉しか知らなかったかもしれない。
だけど、そういう言葉を与えても良いんだと思える。それがとても大事なことなのです。
あるいは、あなたは今まで、自分に対して与えることのできる言葉を知らなかっただけなのかもしれません。言葉を覚えることで、人は手段を持ち得ます。
今回のケースで言えば、あなたは自分で自分にエネルギーを与える手段を得られるかもしれないということです。
優しさは強さのはじまり
自己肯定感の回復とは、自分を責める声を減らすということだけではありません。
責める声が聞こえてきた時に、それとは違う優しい声を、自分の意志で選択できるようになる、ということです。
自分に優しくすることは、決して弱さや甘えではありません。
それは、傷ついた自分を癒し、再び立ち上がるためのエネルギーを内側から生み出す、最も賢明で、力強い「強さ」なのです。
この「自分への優しさ」が心の土台に根付いてくると、次はそのエネルギーを、他者との関係性にも応用していく段階に入ります。
次回は、健全な人間関係を築くための「境界線」というテーマについてお話しします。
(第5回へ)

アルコール依存症当事者です。
2020年7月から断酒しています。
ASK公認依存症予防教育アドバイザー8期生