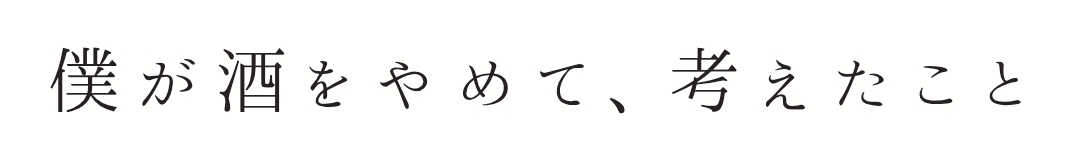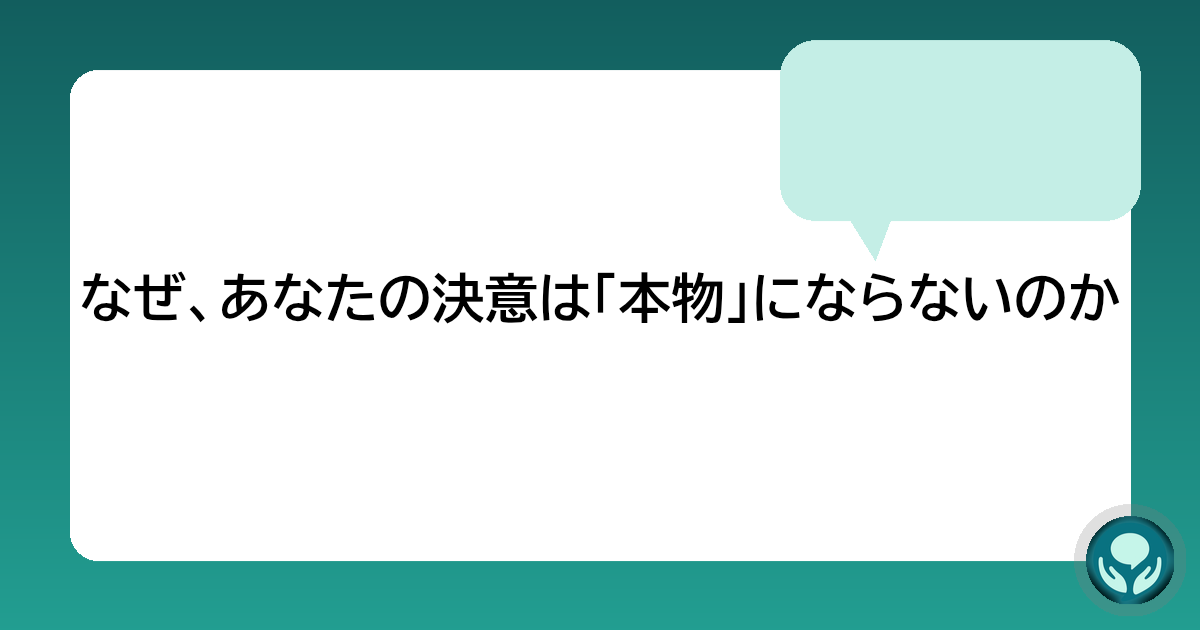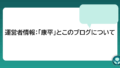「今日こそ、もうお酒は飲まない」
そう固く誓ったはずなのに、夕暮れが迫るにつれて心が揺らぎ、気づけばまた同じ過ちを繰り返してしまう。
そして、深い自己嫌悪に陥る。
「どうして自分はこんなに意志が弱いのだろう」と。
もし、あなたがそんな経験を繰り返しているのなら、それは決してあなたの「意志」だけの問題ではないのかもしれません。
その心の動きを、ある方が提唱した「右足と左足」のたとえ話を通して、少し違った角度から眺めてみませんか。
決意とは、まだ体重の乗っていない“右足”
まず、人が二本の足で立っている姿を想像してみてください。
お酒に頼っている時の心は、その体重のほとんどを「飲んでいる自分」である“左足”に乗せている状態に似ています。
もう随分前からそうしているので、その立ち方自体が当たり前になっているのです。
お酒という杖に頼りながら、片足で必死にバランスを取っているとも言えます。
では、もう一方の「本来の自分」である“右足”はどうなっているでしょう。
地面に触れてはいるものの、体重はまったくかかっていません。
「お酒をやめよう」という決意は、この“右足”に意識を向け、「よし、こちらに体重を移そう」と試みる瞬間のことです。
しかし、多くの場合、その決意は“右足”のつま先を、そっと地面に触れさせてみるだけで終わってしまいます。
傍から見れば、あるいは自分自身でさえも、「やめるための第一歩を踏み出している」ように見えます。
昨日までとは違う行動です。
だから「今度こそはやめられる」という希望さえ抱きます。
しかし、肝心の“重心”は依然として、びくともせずに“左足”の上に乗ったままなのです。
これが、「決意が本物にならない」ことの正体、心の中で起きているカラクリではないでしょうか。
変化がもたらす“痛み”と“恐怖”
では、なぜ重心を移せないのでしょう。
それは、本気で“右足”に体重を乗せようとすると、心身に想像以上の“痛み”と“不快感”が襲いかかるからです。
長い間使っていなかった“右足”に全体重を預けようとすれば、ズキズキとした痛みや痺れを感じます。
筋肉が悲鳴をあげるのです。
それと同時に、これまで全体重を支えてきた“左足”も、急に負荷が抜けることで、かえって不自然な、気持ちの悪い感覚に襲われます。
この両足から同時に発生する不快感。
それは「このやり方は間違っているんじゃないか」と思わせるのに十分なほどの違和感です。
そして、その先には「このまま右足で立ち続けられるのか」「そもそも、この足で踏み出す先に、固い地面はあるのか」という、未知への底知れない“恐怖”が待っています。
その“痛み”と“恐怖”に怖気づいた心は、次の瞬間、無意識のうちに最も慣れ親しんだ体勢、つまり“左足”に重心を戻してしまうのです。
どれだけ苦しい場所であっても、そこは勝手知ったる「いつもの場所」だからです。
断酒とは「我慢をやめる」こと
「では、その痛みにひたすら耐えるのが断酒なのか?」
そう思われるかもしれません。
しかし、ここにもう一つの、とても大切な視点があります。
それは、断酒とは「我慢を始めること」ではなく、むしろ「我慢をやめること」だという逆説的な真理です。
考えてみれば、そもそもなぜ、私たちは“左足”一本で立つような、不自然で苦しい生き方を始めたのでしょうか。
それは、“本当の自分”(右足)で世の中と向き合うことに、耐えがたい“痛み”や“苦しみ”を感じていたからに他なりません。
不安、孤独、欠乏感、恥……そうした感情に耐えるために、感覚を麻痺させてくれるお酒という杖を手に取り、心をかばうようにして生きてきたのです。
つまり、飲酒とは、人生の苦しみを「我慢する」ための一つの手段だった、と言えるかもしれません。
そうであるならば、本当の回復とは何でしょう。
それは、お酒を我慢するという新たな「我慢大会」を始めることではありません。
そうではなく、「そもそも、なぜ自分はこんなにも我慢をしながら生きなければならなかったのか?」と、自分の心の痛みに向き合い、その痛みを和らげる方法を学び直していくプロセスです。
杖を無理やり手放すのではなく、杖がなくても立てる“右足”の筋力を少しずつ取り戻していくこと。
そして、自分の足で大地を踏みしめる感覚を、ゆっくりと身体に思い出させてあげること。
もし、あなたの決意が今日も揺らいでしまったとしても、自分を責めすぎないでください。
それは、あなたの心が未知なる恐怖から、必死にあなた自身を守ろうとした結果なのかもしれないのですから。

アルコール依存症当事者です。
2020年7月から断酒しています。
ASK公認依存症予防教育アドバイザー8期生